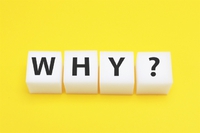2019年10月23日
「いじめ」は誰のもの?
テレビや新聞を賑わす「教師間いじめ」は、社会問題になりつつあります。その報道やtwitterなどの感想を見ながら、私は次の「いじめ」が始まっていると感じます。「信じられない」「よくあんなこと出来るね」「あの人たちを徹底的に罰するべき」
皆さんの善い心がそれを言わせているのはよくわかります。それはもちろん正しいことなのでしょうが。私は不安を感じます。
「正義」の名の下に、私たちが今度は次のいじめの傍観者になっているのではないか、と。
あるテレビ番組の爆笑問題の太田光氏の言葉が引っかかりました。そもそも「いじめは楽しいという本能が人にはあるのだ」ということ。
これには「確かに」という声と「そんな気持ち、自分にはない」という声で世論も二分されていると聞きますが、私はそこに「いじめ問題」の鍵があると思います。私自身は特性上テレビのお笑いの「いじり」も受け付けません。過去にいじめられたこともあります。それでも、自分の中に「人が困っている場面が面白い」と感じる心が全くないとは言い切れないな、と思いました。テレビのバラエティーでこれだけ「いじり」がもてはやされているのは、ニーズがあるからです。いじられた人が困っているのを見て大笑いしている人が、「いじめなんて信じられない」と自分とはまるで他の星の生物みたいに人を判断することに違和感を覚えます。それぞれの皆さんが自分の中にもそんな気持ちがないかと向き合ってみない限りは、この問題は解決しないどころかどんどん次のいじめを産んでいくでしょう。
結局その「人が困っているところ、人の失敗が楽しい」と思う気持ちの延長線上にこの問題があるのです。
太田光氏は自分の「いじり」の基準を「客が引いたらやめる」と言っていました。みんな笑っていましたが、それは大切な一つの基準。自分が周りにウケてどんどん調子に乗ってしまった時、それを止められるのはやはり周りの人。その周りの人の役割が機能しているかどうかは怪しいものですが、本来社会はそうやって成り立つのが理想だと思うのです。
自分の中にある「人が困るのを見て笑ってしまう」という気持ちに蓋をするのは簡単。今まで皆がそうして美しい自分を演じて来ました。しかしそんな感情があるからこそ、どうやってそれをコントロールするか、というところに立って初めて私たちはその感情や行為と共存することが出来るのです。そんな自分の心に蓋をして見て見ぬ振りをし続けることは、結局傍観する側に回るだけ。
「相手の立場に立って」とは小学校の道徳でかなり言われてきた言葉ですが、それは良くも悪くも「道徳」という時間に限られた現実味のない言葉になってしまいました。感想文や反省文にそう書けば、なんとなくサマになります。しかしこれからの私たちは形ばかりでなく、本当に自己と向き合い自分の弱さを自分が感じてそれをどう乗り越えていくか、を考える必要があります。
先生や親に「お前は弱いからなんとかしろ」とか「人の立場に立って考えているか」とか、「反省文を書け」とか。全て人から与えられ続けて考えた振り、向き合った振りをするのではなく、本当に自分の言葉で深い話が出来る様になれば良いのです。残念ながら、今そんな話が出来る場所を探すのは難しいでしょう。なぜなら、日本人は口を開けてじっとしていれば、誰かが何かを入れてくれて、どこかに連れて行ってくれることに慣れてしまっているから。そこにいるだけで、倫理的なものの考え方まで人が教えてくれるのです。コピーペーストしていれば、なんとなく馴染めてしまうのです。
文科省が新しい教育改革で求める「主体性を持った」人は、実際本当に危機的に少なくなっていて、みんなその他大勢の中に溶け込むことに必死になっています。今起こっている様々な問題に大人が真剣に取り組む姿勢を今見せておかなければ。子どもたちは見ています。
今の私たちの立ち振る舞い、覚悟が日本の未来を左右すると真剣に思うのです。
皆さんの善い心がそれを言わせているのはよくわかります。それはもちろん正しいことなのでしょうが。私は不安を感じます。
「正義」の名の下に、私たちが今度は次のいじめの傍観者になっているのではないか、と。
あるテレビ番組の爆笑問題の太田光氏の言葉が引っかかりました。そもそも「いじめは楽しいという本能が人にはあるのだ」ということ。
これには「確かに」という声と「そんな気持ち、自分にはない」という声で世論も二分されていると聞きますが、私はそこに「いじめ問題」の鍵があると思います。私自身は特性上テレビのお笑いの「いじり」も受け付けません。過去にいじめられたこともあります。それでも、自分の中に「人が困っている場面が面白い」と感じる心が全くないとは言い切れないな、と思いました。テレビのバラエティーでこれだけ「いじり」がもてはやされているのは、ニーズがあるからです。いじられた人が困っているのを見て大笑いしている人が、「いじめなんて信じられない」と自分とはまるで他の星の生物みたいに人を判断することに違和感を覚えます。それぞれの皆さんが自分の中にもそんな気持ちがないかと向き合ってみない限りは、この問題は解決しないどころかどんどん次のいじめを産んでいくでしょう。
結局その「人が困っているところ、人の失敗が楽しい」と思う気持ちの延長線上にこの問題があるのです。
太田光氏は自分の「いじり」の基準を「客が引いたらやめる」と言っていました。みんな笑っていましたが、それは大切な一つの基準。自分が周りにウケてどんどん調子に乗ってしまった時、それを止められるのはやはり周りの人。その周りの人の役割が機能しているかどうかは怪しいものですが、本来社会はそうやって成り立つのが理想だと思うのです。
自分の中にある「人が困るのを見て笑ってしまう」という気持ちに蓋をするのは簡単。今まで皆がそうして美しい自分を演じて来ました。しかしそんな感情があるからこそ、どうやってそれをコントロールするか、というところに立って初めて私たちはその感情や行為と共存することが出来るのです。そんな自分の心に蓋をして見て見ぬ振りをし続けることは、結局傍観する側に回るだけ。
「相手の立場に立って」とは小学校の道徳でかなり言われてきた言葉ですが、それは良くも悪くも「道徳」という時間に限られた現実味のない言葉になってしまいました。感想文や反省文にそう書けば、なんとなくサマになります。しかしこれからの私たちは形ばかりでなく、本当に自己と向き合い自分の弱さを自分が感じてそれをどう乗り越えていくか、を考える必要があります。
先生や親に「お前は弱いからなんとかしろ」とか「人の立場に立って考えているか」とか、「反省文を書け」とか。全て人から与えられ続けて考えた振り、向き合った振りをするのではなく、本当に自分の言葉で深い話が出来る様になれば良いのです。残念ながら、今そんな話が出来る場所を探すのは難しいでしょう。なぜなら、日本人は口を開けてじっとしていれば、誰かが何かを入れてくれて、どこかに連れて行ってくれることに慣れてしまっているから。そこにいるだけで、倫理的なものの考え方まで人が教えてくれるのです。コピーペーストしていれば、なんとなく馴染めてしまうのです。
文科省が新しい教育改革で求める「主体性を持った」人は、実際本当に危機的に少なくなっていて、みんなその他大勢の中に溶け込むことに必死になっています。今起こっている様々な問題に大人が真剣に取り組む姿勢を今見せておかなければ。子どもたちは見ています。
今の私たちの立ち振る舞い、覚悟が日本の未来を左右すると真剣に思うのです。
Posted by Nami sensei at 08:41
│Nami先生のつぶやき│Nami先生の育児コラム