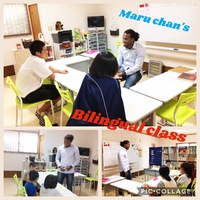2017年04月25日
宿題は信頼関係

今日は教室のニューズレターと連動させて…宿題に関するお話です。
私が1歳児から大人の皆さんまでご指導していて見つけた事実。
『宿題は信頼関係です』
私は常日頃から、我が子や生徒の皆さんを『人から応援してもらえる人』に育てたいと思っています。もちろん私も皆さんの応援団であり続けたい。この『私との人間関係が、目の前にいるあなたの根っこを育てている』ことを信じて、あなたのことを信じ抜きます。
でも同時に、私が皆さんを理解し愛して応援出来る時間は限られていることも知っています。
人は常に動いて、その先々で新しい出会いをし、たくさんの人との関わりの中で人生を過ごします。私の願いは、どこにいっても、どんな人達と出会っても、人に助けてもらえる様な人になってほしい、それだけです。
そうなるためには、人との信頼関係をしっかり築く事が出来る人を育てなければいけません。
そこでふと、気付いたことがありました。「たかが宿題、されど宿題。」
私がいくら応援したいと願っても、毎回宿題をしてこない。平気な顔をしてレッスンを受けてまた翌週も宿題をしてこない。先生として正直な気持ちを言わせていただくと、「この子は伸びようとは思っていないんだ」そう判断されてもおかしくない。じゃ、私がそこまでこの子を伸ばす努力をする必要もないのかな…と。私はそんな気持ちになりそうな自分をグッと引き戻して、ではどんな宿題だったら出来そうかな…と工夫をしたり話し合ったりします。しかし、宿題をする習慣のついていない生徒はどんな方法を取っても宿題をしません。中には「学校のは怒られるからするけど」という生徒もいます。
習慣を作るには、人の力を必要とします。特に子どもの場合は、大人の力で簡単に良い習慣が身につきます。生活を共にしている大人の働きかけが大きな役割を持つことは言うまでもありません。怒られるから…も一つのモチベーションになるのかも知れませんが、怒られなくても毎日の習慣の中に入れてしまうと、本人にとってはだんだん苦ではなくなってくるものです。
『宿題をしないと学校の授業についていけないのではないか』『先生に叱られるのではないか』
皆さんは宿題に関してまず、そういう印象を持たれるかも知れませんが、実はそんなに一時的な問題ではないのです。それ以上の「信頼関係」に関わる大切なことなのです。
どうしても出来ない事情があった、宿題が多過ぎて無理…そんな場合は、きちんと出来なかった理由を言って詫びる、また宿題が多過ぎる事を伝えて一緒に量を考えてもらう、それも大切な力です。これは学校や教育現場の問題です。子どもが「自分の言うことを聞き入れてもらえる」と安心出来る環境を作る、それが今後多様化、グローバル化していく社会を作る基礎になるでしょう。ここでも思うのです。「黙ってついてくる者だけを善しとする教育を続けていてはいけない」と。
宿題、という先生との約束を守ることが前提なのか、簡単に破って理由も言わずにやり過ごすのか、ただ叱られて終わるのか、それには「宿題」という言葉以上に大変大きな学びがあることを、私達は心に留めて子どもたちと関わる必要があると思います。